トランスクリプション
- cphmn700
- 2021年9月4日
- 読了時間: 2分
ウクレレの編曲、というかトランスクリプション作業なんだけど、クラシックギターの曲を移すのが面白いのです。
まず、やってみようと思ったのが、タルレガの「ラグリマ」。

タルレガはスペインの19世紀から20世紀初めの作曲家、ギタリスト。ギター曲をいっぱい書いてくれました。それまでの古典的な作曲ではなくて全然違うギターの使い方をした作曲をした人です。
「ラグリマ」は、学生時代に一番初めに弾けるようになったギター曲。涙という意味です。コンクールの課題曲でもありました。
タルレガの曲の中では一番弾きやすい曲だと思います。
運指をギターとほぼ一緒にするために、調を変えました。原曲はEメジャーだけど、ウクレレではAメジャー。途中のEマイナーのところは当然Aマイナーです。
案外うまくいったと思う。でも、低音欲しいよなーってすごく思うんですよねー。
5弦と6弦が欲しい。。。あ、でもウクレレ縛りで編曲するんやった。ないものはないのだ!
ちなみに、もう1曲、「マリーア」もやりました。こっちは同じ調にしました。
次にやってみたのがヴィラ=ロボス。

ブラジルの19〜20世紀の作曲家で、ギター曲もいくつか有名なものがあります。
現代的な音の使い方は、クラシック音楽とはちょっと違うところも匂わせ、今聴いても胸が高鳴るのです。
ウクレレに移した曲は「前奏曲3番」。
これは、ギターで弾きたかったのですが、ちゃんとやってなかったんですよねー。で、ウクレレでやってやろうと。左手は同じ形で動くところが多いので弾けるんちゃう?と思ってたのですが、いくつか問題が。
ひとつは、スケールで上昇するところ(16分音符4つでひとかたまり、それがオクターブで上がっていって、スケールのようになっている)が、音域が足りなくてできない。なんかアルペジオみたいになっちゃった。もうひとつは、同じコードフォームで動くところ、実は開放弦を紛れ込ませていて、それを一緒に弾くので変わった和音になるところ、その開放弦を入れられないので普通のコードを並行移動させてるだけになる。
うーん。こういうところがヴィラ=ロボスの個性的なところなのにそれを入れられない。難しいよ。
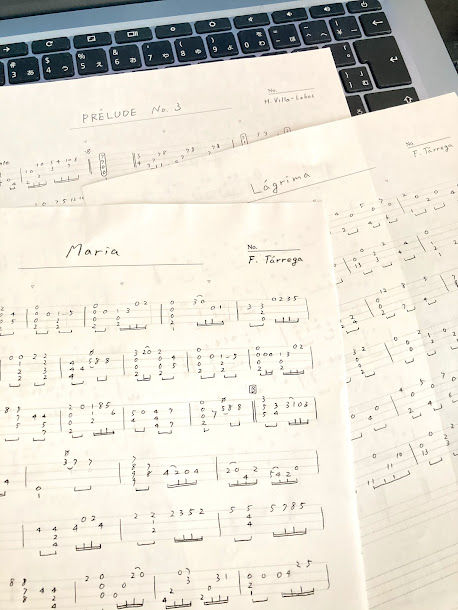
やっぱりギターで弾いたほうがいいよね。
でも、ギターもウクレレも弾く人間にとっては、ちょっとやってみたくなるものなのだよ。
割と細かく中身を見れたのでよしとするか。
クラシックギター奏者のみなさん、暖かい目で見てちょうだい。怒らないでね。





コメント